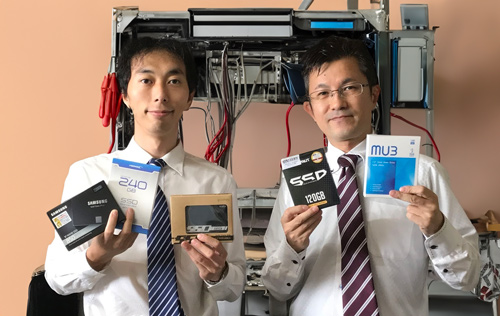感染に気づいたら最初にすべきこと
ノートパソコンを開いた途端、身に覚えのない警告音と共にブラウザが勝手に立ち上がったら、多くの人は思わず画面を閉じてしまいます。
しかしその動きはマルウェア感染による典型的な症状で、慌てて操作すると被害が広がる恐れがあります。
まずはインターネット接続を切り、外部への通信を遮断することが被害拡大防止の第一歩です。
有線LANならケーブルを抜き、Wi‑Fiならルーターの物理スイッチをオフにします。
その上で最新のウイルス定義ファイルを適用したセキュリティソフトで完全スキャンを実施しましょう。
もし既存のソフトが動かない場合は、安全な別端末で公式サイトからオフラインインストーラをダウンロードし、USBメモリで移す方法が有効です。
マルウェアとは?基本概要
マルウェアは悪意あるソフトウェアの総称で、ウイルス、トロイの木馬、ランサムウェアなど多岐に渡ります。
2024年の統計によると、生成AIを使って自動でコードを書き換える自己改変型マルウェアが急増しています。
攻撃者は脆弱なブラウザ拡張機能や偽装アップデートを通じて侵入し、情報窃取や広告表示で利益を得ます。
Windows11だけでなくMacも標的にされており、「Macは安全」という神話は過去のものになりつつあります。
さらにスマートフォンとクラウドで連携している場合、同期データを経由して別デバイスへ感染が拡大することがあります。
被害を最小限に抑えるためには、OSやアプリを常に最新の状態に保つことが前提となります。
症状と感染経路を知る
突然ポップアップが連続しブラウザが強制的に再起動する場合、広告系マルウェアの可能性が高いです。
CPUやファンの回転が常に高い状態なら、仮想通貨のマイニングマルウェアが動作しているかもしれません。
ランサムウェアの場合はファイル名が書き換えられ、復号キーを要求する脅迫文が表示されます。
メールに添付されたZipファイルや不正なPDFを開いた直後に感染報告が多く、依然としてフィッシングメールは主要な経路です。
海賊版ソフトのダウンロードサイトや、ストリーミングの不審なプラグイン経由でも感染例が報告されています。
2024年春のIPA注意喚起では、偽ChatGPTアプリを装ったマルウェアが国内で拡散したと発表されました。
感染経路を把握しておくことで、今後の再発防止策を具体的に講じることができます。
安全な削除手順
手順1 セーフモードで起動する
システムに常駐したマルウェアは通常モードでは停止できないため、Windows11なら設定から「回復オプション」、Macなら電源ボタン長押しでセーフモードを選択します。
セーフモードでは不要なドライバが読み込まれないため、不審なプロセスを見つけやすくなります。
手順2 不審なプロセスとプログラムを削除
タスクマネージャーやアクティビティモニタでCPUを占有する見覚えのないプロセスを確認し、ファイルの場所を開いて削除します。
続いて「アプリと機能」または「アプリケーション」フォルダから正体不明のソフトをアンインストールします。
手順3 ブラウザ設定をリセット
ChromeやEdgeで検索エンジンが勝手に変わっていたら、設定画面から初期化を実行してください。
拡張機能も同時に確認し、ダウンロード元が不明なものはすべて無効化または削除します。
手順4 レジストリとスタートアップを確認
Windowsの場合「regedit」で自動起動項目を検索し、GUIDだけで構成されたキーは特に要注意です。
スタートアップフォルダやサービスに残っていると再起動後に復活するため、併せて無効化します。
手順5 バックアップの確認とデータ復旧
削除作業の前後でファイルが失われた場合、上書き前なら復旧ソフトで取り戻せる可能性があります。
インフォムPC工房でも、SSDからのデータ復旧を行った実績がありますが、暗号化ランサムウェアでは復旧率が下がる点に注意が必要です。
費用と時間の目安
自力でのマルウェア削除はソフト代のみで済みますが、作業時間は平均3〜4時間ほどかかります。
専門業者へ依頼した場合、診断料金が数千円から、駆除作業は内容により数万円程度が一般的です。
ランサムウェアで暗号化された場合は、復号調査に追加費用が発生し、1週間以上かかることもあります。
特に業務用PCで稼働停止が許されない場合は、迅速な対応を優先し、費用よりダウンタイムの短縮を重視する判断が求められます。
個人利用でも写真や確定申告データが失われるリスクを考えると、バックアップと合わせて専門相談する価値はあります。
費用感は症状や機種により変動するため、見積もりは複数社で比較するのが無難です。
インフォムPC工房の見解とサポート
当社サイトInfomPC.comでは、マルウェア駆除とデータ復旧の事例を定期的に公開しています。
2024年の社内統計では、リモートワーク端末の約8%が何らかのマルウェアに感染しており、USBメモリ経由の持ち込みが最多でした。
インフォムでは持ち込み診断のほか、法人向けにエンドポイント監視ツールの導入支援も行っていますが、記事全体を通じて中立的な情報を提供する方針です。
症状の重さやデータの重要度に応じて、駆除のみ、データ復旧併用、買い替え提案など複数の選択肢を提示することを心掛けています。
まとめと再発防止策
マルウェア感染は予期せぬタイミングで発生しますが、冷静にネット接続を遮断し、セキュリティソフトで隔離するだけでも被害は大幅に軽減できます。
OSとアプリのアップデート、自動バックアップ、信頼できるサイトからのダウンロードを徹底することで再発リスクは下がります。
ランサムウェアなど深刻なケースでは専門業者の助けが必要となるため、早めに相談窓口を把握しておくと安心です。
本記事を参考に、パソコンの健康状態を定期的にチェックし、安全で快適なデジタルライフを維持してください。