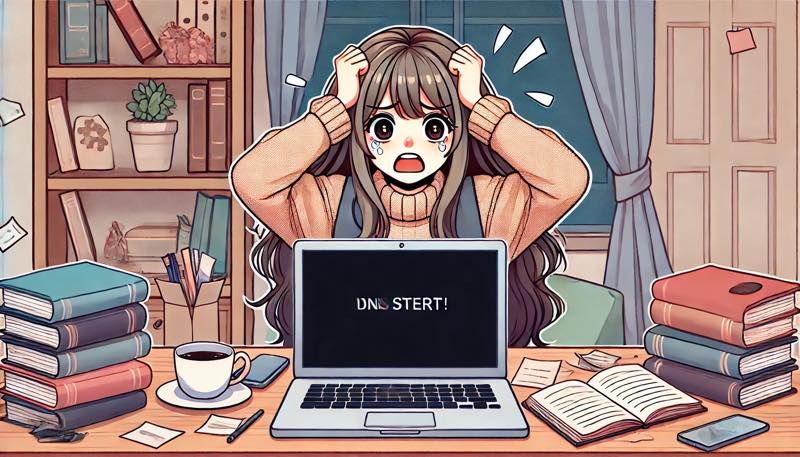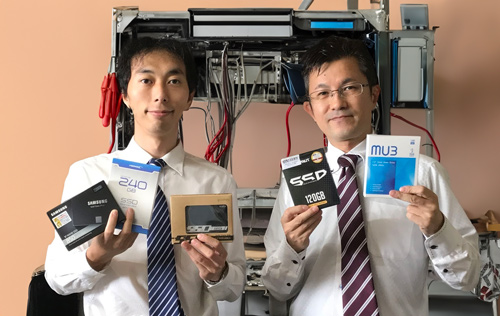突然パソコンが起動しない…その焦りに共感します
電源ボタンを押しても画面が真っ暗のままという状況は唐突に訪れます。
資料の締め切りが迫っていたりオンライン会議の直前だったりすると心拍数が一気に上がります。
特にノートパソコンはバッテリー頼みの場面も多く原因の切り分けが複雑になりがちです。
本記事では最新の技術情報とインフォムのサポート実績を参考にしながら「パソコン 起動しない」問題を体系的に整理します。
緊急対処からデータ復旧の可能性まで幅広く網羅するので一歩ずつ確認してみてください。
まずは落ち着いて試す緊急チェックリスト
電源周りの確認
ACアダプターがしっかり差し込まれているか壁側コンセントまでたどって確認します。
タコ足配線や延長コードを介している場合は直接壁のコンセントに挿してみると改善する例があります。
ノートパソコンならバッテリーを一度外しACアダプターのみで起動できるか試しましょう。
デスクトップの場合は電源ユニット裏のスイッチがオフになっていないかも意外と盲点です。
放電リセットを行う
マザーボードに帯電している静電気が起動を妨げるケースがあります。
電源ケーブルとバッテリーを外し電源ボタンを20秒以上長押しして放電させてから再接続します。
この手順だけで復活する割合はメーカーサポートでも十数パーセントあると言われています。
外部機器をすべて取り外す
USBメモリや外付けHDDが起動時のブートシーケンスを妨げることがあります。
接続機器を全て外してから起動できるか確認し変化を見ます。
モニターケーブルやドッキングステーションも含めて最小構成にするのがコツです。
起動しない主な原因を理解する
ハードウェアトラブル
電源ユニットの故障やマザーボードのコンデンサ劣化は定番の原因です。
SSDやHDDが物理的に壊れた場合はBIOSすら開けないこともあります。
2024年に報告されたIntel第11世代モバイルCPU搭載機の一部では電源管理ファームウェアの不具合で突然起動しなくなる事例が確認されています。
ソフトウェア・設定の問題
Windowsアップデートの失敗やドライバー競合でブートローダーが破損すると起動ループが発生します。
BitLockerやファームウェアパスワードが絡むと間違ったキー入力が続きロックアウトされることもあります。
最近増えているのがBIOS設定の「高速起動」が周辺機器と相性問題を起こしブラックアウトするパターンです。
症状別の具体的な解決策
電源は入るが画面が真っ暗
ファンやLEDが動いている場合は内部ディスプレイケーブルの断線やグラフィックチップの発熱不良を疑います。
外部モニターを接続して映像が出るか確認することで原因の切り分けが可能です。
外部にも映らない場合は内部メモリが正しく装着されているか抜き差ししてチェックします。
電源が全く入らない
電源ボタン基板とマザーボードをつなぐフレックスケーブルが断線している事例がノートパソコンで増えています。
修理ではケーブル交換と電源ユニット診断をセットで行うのが一般的です。
デスクトップなら市販の電源テスターで12Vラインが供給されているか測定すると故障箇所を特定できます。
Windowsロゴが出たあと再起動を繰り返す
スタートアップ修復を自動で試みるループはシステムファイル破損が濃厚です。
回復環境で「システムの復元」を実行し直近の復元ポイントに戻すと改善する場合があります。
復元ポイントが無い場合は別PCで作成したUSBインストールメディアから「修復」を選びコマンドプロンプトでbootrec /fixmbrを実行する手段も有効です。
データを守りながら復旧する方法
起動しない状態でもストレージ自体が無事ならデータ復旧の成功率は高いです。
ストレージを取り外し別のパソコンにUSB接続してバックアップを確保するのが安全な第一歩です。
自力で取り外しが難しい場合は無理に分解するとコネクタを破損しかねないので専門業者へ依頼しましょう。
インフォムの2024年サポート事例では起動不良からのデータ救出成功率が約92%と報告されています。
ただし物理障害のあるSSDはチップオフ解析が必要になり費用も期間も大きく跳ね上がる点に注意が必要です。
修理に出す前に押さえておきたい費用と期間の目安
一般的に電源ユニット交換は部品代込みで1万円台から3万円程度と言われています。
マザーボード交換になるとメーカー正規だと5万円を超えることも珍しくありません。
データ復旧は論理障害なら数万円前後ですが物理障害になると十万円を超えるケースもあります。
修理期間は部品在庫が国内にあるかで大きく変動し最短即日から最長数週間が目安です。
メーカー保証が残っているかどうかで選択肢も違うためシリアル番号と購入時期を手元に用意して問い合わせるとスムーズです。
プロに依頼するか自力で直すかの判断基準
保証期間内で公式サポートが受けられる場合は分解を行わずにメーカーへ送るのが鉄則です。
バックアップが取れていない重要データがある場合はデータ復旧を重視する専門業者を選ぶ必要があります。
ハードウェア診断ツールが扱える経験者であれば電源ユニットやメモリ交換を自力で試す価値があります。
一方基板レベルの半田修理やBIOS ROM書き換えは設備とスキルが必須なためプロ依頼が賢明です。
インフォムでは症状診断は無料見積もりで行い修理をキャンセルしても診断料はかからない方針を取っています。
最新動向と専門家コメント
2024年4月にMicrosoftはWindows11のスタートアップリカバリーを強化するアップデートを発表しました。
これにより従来より自動修復の成功率が上がるとされていますがハードウェア故障の場合は効果がありません。
日本電子機器修理協会の山田氏は「ユーザーは電源トラブルとストレージ故障の区別がつかないことが多く分解前の電圧測定が重要」と述べています。
起動不良を複合的な視点で診断することが成功の鍵である点は現場でも一致する見解です。
まとめ:一つずつ原因を切り分ければ慌てず対処できる
パソコンが起動しない時はまず電源と外部機器を確認し放電リセットを試すことで解決することがあります。
次にハードウェアとソフトウェアの両面から原因を把握し適切な手を打つことが重要です。
データが最優先ならストレージを取り外しバックアップを先に確保する判断が被害を最小化します。
費用や期間の目安を把握したうえで自力対応と専門業者依頼を使い分けましょう。
本記事があなたの大切なノートパソコンやデスクトップを再び動かす手助けとなれば幸いです。