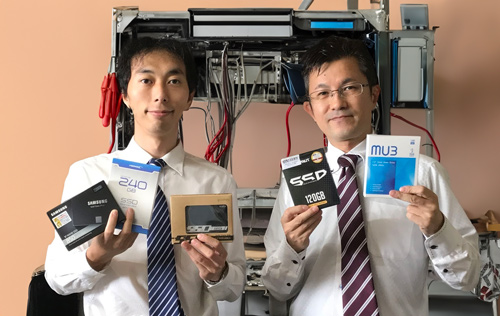会社のパソコンが突然故障したとき、まず何をすべきか
取引先への見積書を印刷しようとした矢先、オフィスのメインPCが突然起動しなくなった経験はないでしょうか。
社内に常駐するシステム担当者がいない中小企業では、1台のパソコン故障が即、業務停止につながります。
本記事では会社のパソコンが故障した際に取るべき緊急対応から修理・交換の判断基準、さらに再発防止策までを網羅的に解説します。
ノートパソコンやMacなど機種を問わず活用できる具体策を紹介するので、いざというときの備えとしてご活用ください。
故障の主な原因と背景を理解する
ハードウェア起因の故障
HDDやSSDの物理的損傷、マザーボードのコンデンサ破損、ファンの劣化による熱暴走などが代表例です。
2024年の半導体不足の影響で一部部品の調達期間が長期化しており、修理に要する日数が伸びる傾向にあります。
ソフトウェア・OS起因の故障
Windows Updateの失敗やドライバー不整合が起動不良を招くケースが増えています。
Microsoftは2024年4月にファームウェアの自動更新失敗率を公表し、ブルースクリーン発生率が0.15%上昇したと報告しました。
環境・ヒューマンエラー
コーヒーの水こぼし、落下、過剰な電源タップ使用による過電流など、人為的要因も無視できません。
インフォムの実績として、水濡れ直後に通電を止めたケースでは約70%のデータ復旧成功率が報告されています。
緊急対応の具体的な手順
初期診断のポイント
電源ランプが点灯するか、ビープ音が鳴るかなど最低限のハードウェアチェックを行います。
通電しない場合は電源ユニット、通電するが画面が真っ暗な場合はメモリやGPUを疑います。
データ保護とバックアップ
業務用パソコンではデータ損失が最も大きな損失となるため、故障が疑われた段階でストレージを外し、別PCでイメージバックアップを取得してください。
RAIDやNASを利用している場合はリビルド前に全体スナップショットを取得すると復旧率が上がります。
社外サポートへの連絡
保守契約がある場合は症状とエラーメッセージを正確に伝え、ログのスクリーンショットが取れるなら共有します。
契約がない場合も、症状を録画しておくと診断がスムーズになります。
修理・交換・代替機手配の流れ
故障機の診断結果がハードウェア不良と判明したら、修理か本体交換かを選択します。
一般的に3年以上使用したパソコンは部品供給が終了していることが多く、代替機手配のほうが早期復旧につながります。
データ復旧が必要な場合はストレージだけを専門業者に預け、復旧データを新PCへ移行する方法が推奨されます。
インフォムでは当社調べで平均3営業日以内に代替機を用意し、イメージ展開を行うことで業務停止時間を短縮した事例があります。
費用と期間の目安
部品交換のみで済む軽微な修理は一般的に数千円から数万円程度、マザーボード交換やデータ復旧を伴う重度故障では数十万円に達する場合があります。
期間は症状と部品在庫で大きく変動し、在庫がある軽作業なら即日、部品取り寄せが必要な場合は1〜3週間が目安です。
クラウドストレージにバックアップがある企業はデータ復旧費用を抑えられ、代替機コストのみで済むケースが増えています。
業務継続のための事前備え
BCP策定とクラウド活用
BCP(事業継続計画)にパソコン故障を織り込み、クラウドストレージや仮想デスクトップを併用すると復旧時間を大幅に短縮できます。
2024年2月に公表された総務省の調査では、クラウド活用企業は非活用企業と比べダウンタイムを平均34%削減できたと報告されています。
定期点検と交換サイクル
ファンの埃除去やバッテリーテストを半年ごとに実施し、使用年数4〜5年で計画的リプレースを行うことで突発的な故障リスクを抑制できます。
社員教育
電源タップの過剰使用を避ける、飲み物をキーボード付近に置かないなど基本的なリスク回避を社員向けガイドに明文化しましょう。
まとめ
会社のパソコン故障は業務停止とデータ損失を同時に引き起こす重大インシデントです。
まずは電源を切り、データ保護を最優先に初期対応を行うことが被害拡大を防ぎます。
原因を特定したうえで修理・交換・代替機手配の最適解を選び、費用と期間を見積もりましょう。
クラウドバックアップや定期点検を通じて再発防止策を講じれば、故障が起きても業務継続が可能になります。
本記事を参考に、ぜひ自社のBCPをアップデートし、万一に備えた体制を構築してください。