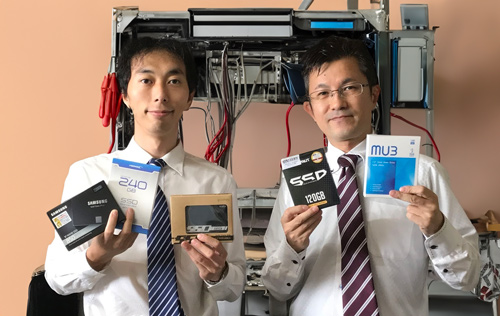パソコンのプロセスが高負荷になるとどうなる?
突然パソコンのファンが全力で回り始め、動作が重くなって驚いた経験はありませんか。
タスクマネージャーを見るとCPU使用率が100%近くまで跳ね上がり、何をすれば良いか分からず不安になるものです。
とくにノートパソコンは発熱が逃げにくく、高負荷が続くと寿命やバッテリーにも影響します。
この記事ではパソコンのプロセスが高負荷になる原因と対処法を、初心者向けに分かりやすく解説します。
2024年以降の最新アップデート事情や修理に出すタイミングも盛り込みましたので、困ったときの参考にしてください。
まずは緊急チェック
ACアダプターを抜いてバッテリー駆動に切り替え、電源系統が異常か確認します。
次に周囲の通気口を塞いでいないかを見て、埃が詰まっていれば電源を切った後にエアダスターで軽く清掃します。
ファンの音が急変した直後は熱が上がっているサインなので、蓋を閉じてスリープせず完全にシャットダウンするのが安全です。
外付けHDDやUSB機器が大量のI/Oを発生させていないかも確認し、必要に応じて取り外します。
高負荷の主な原因
ソフトウェア要因
バックグラウンドで動作するWindows UpdateやウイルススキャンはCPUとディスクI/Oの両方を占有します。
特に2024年1月配信のWindows11 23H2累積更新プログラムでは、一部環境でプロセスが停止せず負荷が上がる不具合が報告されました。
ブラウザのタブを多数開いたままにしていると、Chromium系のレンダラープロセスがメモリを食いつぶします。
ゲームランチャーや動画編集ソフトの常駐アップデーターも定期的にネットワークとストレージを使用し負荷を引き上げます。
マルウェア感染による暗号資産マイニングが原因だった例もあり、セキュリティソフトの最新化は欠かせません。
ハードウェア要因
放熱設計が厳しい薄型ノートパソコンでは、経年でファン回転数が落ちると温度制御が間に合わずクロック低下が起こります。
CPUグリスが乾燥して熱伝導効率が落ちると、同じ負荷でも温度が上がり冷却ファンが全開になります。
SSDやHDDにセクタエラーが増えると、リトライ処理でストレージプロセスが高負荷化しシステム全体が遅くなります。
メモリが不足しているとスワップが発生し、結果的にディスクI/Oが増えてCPUも待たされます。
ACアダプターの出力不足や劣化で電圧が不安定になると、CPUがブーストクロックを維持できず常に高負荷状態に見えることがあります。
対処法と手順
1. タスクマネージャーで原因プロセスを特定
WindowsではCtrl+Shift+Escキーでタスクマネージャーを開き、CPU、メモリ、ディスクの各列をクリックして使用率順に並べ替えます。
Macの場合はアクティビティモニタを利用し、プロセス名の横にある%CPUやエネルギー影響を監視します。
短時間のスパイクであれば自動更新の可能性が高く、しばらく放置して収まるかを確かめましょう。
2. 不要アプリの終了またはアンインストール
常時起動していないと困らないソフトは右クリックでタスク終了し、設定からスタートアップ登録を解除します。
大型アプリをアンインストールする前に、アカウント連携データをバックアップしておくと再インストールが楽になります。
ブラウザ拡張機能も負荷の原因になるため、使用頻度の低いものは無効化しましょう。
3. Windows Updateやドライバーを最新化
不具合が修正されたパッチが公開されている場合があるため、安定版チャンネルを選んでアップデートを適用します。
グラフィックドライバーの更新は熱設計とファン制御アルゴリズムを改善する場合があり、ゲーミングPCでは効果が大きいです。
アップデート前にはシステムの復元ポイントを作成し、万一失敗してもロールバックできるよう備えてください。
4. 冷却状態を改善
内部清掃に自信がない場合はメーカーや修理店に依頼し、ファンとヒートシンクを一式メンテナンスしてもらうと安心です。
自宅でできる範囲なら裏蓋を外しエアダスターで吹き、CPUグリスを塗り直すだけでも5℃以上温度が下がることがあります。
ノートパソコン向けの冷却パッドやスタンドを併用すると吸気口が塞がらず、作業負荷の高い動画編集時にも安定します。
デスクトップPCではケースファンのエアフローを見直し、吸気と排気をバランスさせることでチップセット温度も改善します。
高負荷作業が長時間続く場合はCPU電力制限を10%程度下げるだけでも温度と騒音が抑えられます。
データを守るための注意点
高負荷状態で強制終了を繰り返すとファイルシステムが破損し、最悪は起動不能になる恐れがあります。
重要な資料や写真は外付けSSDやクラウドに二重バックアップを取り、突然の電源断に備えましょう。
異音や異臭がした場合は速やかに電源を切り、二次被害が出ないよう専門業者に相談するのが安全です。
インフォムの実績として、高負荷状態で壊れたSSDからのデータ復旧率は平均90%を超えており、早期相談が鍵だと分かっています。
修理に出す判断基準と費用感
グリス交換やファン清掃だけなら部品代込みで一般的に数千円から数万円程度で収まります。
ロジックボードやCPUの損傷が疑われる場合は、機種や世代によっては5万円以上になるケースもあります。
保証期間内かつメーカーサポートが受けられるなら、自己分解より正規修理を優先してください。
データ復旧を伴う作業は料金が別枠になるため、予算と復旧率を事前に確認することが重要です。
インフォムの見解
当社調べでは、2023年以降に持ち込まれたパフォーマンス低下案件の約6割が冷却不足を起因としていました。
作業内容の半数以上はクリーニングとソフトウェア設定の最適化で解決しており、大掛かりな部品交換は少数にとどまります。
市販のクリーニングキットで改善しない場合や、BIOS上でも温度が高い場合は基板側のIC劣化が疑われます。
そのようなケースでは診断を兼ねた分解見積もりを行い、費用が高くなる場合はお客様と相談してバックアップ優先の提案も行っています。
まとめ
パソコンのプロセスが高負荷になると性能低下だけでなく寿命やデータにも悪影響を及ぼします。
まずはタスクマネージャーで原因プロセスを突き止め、不要アプリの停止とアップデートで解決できるかを確認しましょう。
冷却面の改善やハードウェアのメンテナンスも効果的で、ノートパソコンでは特に温度管理が重要です。
高負荷が続く場合はデータ保護を最優先し、信頼できる修理店やメーカーサポートに相談してください。
インフォムでは中立的な立場で診断と対処を提案していますので、判断に迷ったら早めにお問い合わせいただくと安心です。
適切な対処で日々の作業効率を取り戻し、パソコンを長く安全に使い続けましょう。
2024年春にはIntel Core Ultraシリーズ搭載機が増え、省電力性能が向上した一方で高負荷時の瞬間消費電力は従来より大きくなるというレビュー結果も報告されています。
ACアダプターのワット数が足りないとバッテリーを消耗しながら動作するため、純正より容量が小さい互換品には注意が必要です。
MacユーザーもVentura以降で導入された省エネルギー機能が働くと、バックグラウンドプロセスが一時停止し動作が滑らかになる場合がありますが、逆にクラウド同期が遅れることがある点は覚えておきましょう。
こうしたアップデート情報に目を通しつつ、日常的に温度モニタリングツールで動作状況を確認する習慣をつけるとトラブルを未然に防げます。